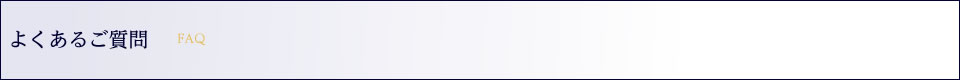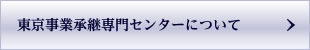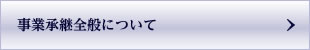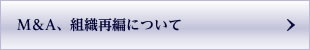その他対策について
名義株について教えてください。また、名義株を整理することの必要性を教えてください。
名義株とは株主名簿に記載されている真の株主ではない株主を言います。平成2年商法改正以前では、会社の設立には7人の発起人が必要であったため、親族、取引先、友人等が名義上の株主となっていることがありました。名義株式を放置しておくと、①事業と無関係の人物が株主として存在し、事業の遂行に支障をきたす可能性がある、②高額での買取を請求される可能性がある、③争族の原因となる可能性がある、④事業承継の手法としてM&A組織再編を選択した場合、税制非適格となる可能性ある等のリスクがあります。従って、名義株は早い段階で整理しておく必要があります。
名義株式を整理する方法を教えてください。
まずは、株主名簿を真実の株主に変更する必要があります。その際、名義貸与株主の承諾がないまま、株主名簿を変更すると、後々、税務上、会社法上、大きなトラブルに発展する可能性があります。従って、名義貸与株主に名義貸である旨の確認書を入手し、その後会社に対して名義書換請求を行い、取締役会の承認を得て、名義を変更する必要があります。確認書を入手できた場合、株式の移転に伴う贈与税は発生しません。
名義株の整理は基本的には、当事者間の話合いで行うことになりますが、場合によっては、金銭の授受が必要になる場合も想定されます。
また、確認書を入手できない場合や話がもつれた場合には、種類株式を用いて強行することになります。その方法は以下のとおりです。
- ①定款の変更を行い、種類株式を発行する旨を定める。
- ②普通株式に全部取得条項を付す旨を定める。
- ③全部取得条項付普通株式の取得を決議し、名義株主から全部取得条項付普通株式を取得する。
種類株式とはどのようなものですか?
種類株式とは、普通株式と権利の内容の異なる株式を発行した場合のその株式のことを言い、以下のようなものがあります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 配当優先株 | 株式ごとに異なる配当ができる。 |
| 残余財産優先分配株式 | 会社の精算における残余財産の分配を優先的に受けることができる。 |
| 議決権制限株式 | 普通株式とは異なる議決権を持たせることができる。 |
| 譲渡制限株式 | 会社の承認を得なければ、株式の譲渡は会社に対する関係では無効とすることができる。 |
| 取得請求権付株式 | 株主が会社に株式の買取を求めることができる。 |
| 取得条項付株式 | 一定の事由が生じた場合に、会社の主導で株式を取得することができる。 |
| 全部取得条項付株式 | 株主総会の特別決議で、会社が株式の全部を強制的に買い取ることができる。 |
| 拒否権付株式(黄金株) | 株主総会の一定の決議事項についてこの権利を持つ株主が同意しない限り、可決できない。 |
| 役員選任解任付株式 | 種類株主総会で、会社の役員(取締役、監査役)を選任すること解任することができる。 |
種類株式の活用局面を教えてください。
種類株式は主に、①株主の分散防止、②現経営者の次期経営者への影響の強化、③事業後継者以外の株主の影響力の抑制、④株式の財産権の価値を高めるために利用されます。各種類株式ごとに活用局面をまとめると、以下のようになります。
| 区分 | 活用局面 |
|---|---|
| 配当優先株 |
|
| 残余財産優先分配株式 |
|
| 議決権制限株式 |
|
| 譲渡制限株式 |
|
| 取得請求権付株式 |
|
| 取得条項付株式 |
|
| 全部取得条項付株式 |
|
| 拒否権付株式(黄金株) |
|
| 役員選任解任付株式 |
|
種類株式を活用する場合の留意点を教えてください。
種類株式を活用する場合の留意点を、各種類株式ごとにまとめると以下のようになります。
| 区分 | 留意点 |
|---|---|
| 配当優先株、残余財産優先分配株式 |
|
| 議決権制限株式 |
|
| 譲渡制限株式 |
|
| 取得請求権付株式 |
|
| 取得条項付株式 |
|
| 全部取得条項付株式 |
|
| 拒否権付株式(黄金株) |
|
| 役員選任解任付株式 |
|
種類株式の発行手続を教えてください。
種類株式の発行手続を各種類株式ごとにまとめると、以下のようになります。
| 区分 | 発行手続 |
|---|---|
| 配当優先株 | 定款に①優先して配当する金額②参加型か非参加型か③累積型か非累積型かを定める必要がある。定款の変更には、株主総会の特別決議が必要。 |
| 残余財産優先分配株式 | 定款に①優先的に交付する残余財産の価額の決定方法②優先的に交付する残余財産の種類、その他分配に関する取扱いを定める必要がある。定款の変更には、株主総会の特別決議が必要。 |
| 議決権制限株式 | 発行可能総数と議決権行使事項、条件等を定款で定める必要があり、定款の変更には、株主総会の特別決議が必要。 |
| 譲渡制限株式 | 譲渡制限のない株式から、譲渡制限株式にするためには、株主総会の特殊決議が必要。 |
| 取得請求権付株式 | 定款に①取得に対価②算定方法③請求できる期間を定める必要があり、定款の変更には、株主総会の特別決議が必要。 |
| 取得条項付株式 | 定款に①取得事由②取得の対価等を定める必要があり、定款の変更には株主総会の特別議が必要。また、発行済みの全株主に取得条項を付ける場合には、株主全員の同意が必要。 |
| 全部取得条項付株式 | 普通株式を全部取得条項付株式に変更する旨の定款変更を行い、株主総会の特別決議で承認を得る必要がある。なお、これに反対する株主は、株式買取請求権を行使することができる。 |
| 拒否権付株式(黄金株) | 定款に拒否権の発動の対象となる株主総会の決議事項を定める必要があり、定款の変更には、株主総会の特別決議が必要。 |
| 役員選任解任付株式 | 定款に①種類株主総会において選解任する取締役、監査役の数②他の種類株主総会と共同で取締役、監査役を選任する場合はその数等 |
* 前提として種類株式を発行する旨の定款変更を行い、株主総会の特別決議による承認が必要。
属人的株式とは何ですか?
属人的株式とは、株式ではなく特定の人自体に剰余金の配当、残余財産の分配、議決権について権利を与える制度を言います。従って、権利が人という個人に帰属しているため、株式の移転により株主が分散することもなく、他人に株式が渡っても権利は移転しません。
属人的株式の活用局面、留意点を教えてください。
属人的株式は定款自治を最大限に利用したものであるため、様々な場面での活用が想定されます。具体的には、現経営者が一定の影響力を残しておきたい場合、次期経営者以外の相続人との公平を図る場合、会社に好ましくない者が経営に関与することを防止する場合になどに活用することができます。しかし、属人株式は特殊な制度であるため、以下の点には留意する必要があります。
- ①属人的株式の内容については、株主総会の特殊決議が必要(総株主かつ総株主の議決権の3/4以上の同意)
- ②税務上明確に規定されていないため、同族会社の判定、株式評価を慎重に検討する必要がある。
- ③属人的株式の内容は社会通念上認められる範囲にとどめておく必要がある。
そろそろ引退して事業を息子に譲ろうかと考えております。しかし、息子が事業を承継するための資金を有しておりません。このような場合資金調達の方法を教えてください。
事業承継における資金調達として、以下のような方法が考えられます。
- ①民間金融機関からの融資
- ②政府系金融機関からの融資
- ③信用保証協会による信用保証
- ④ファンドを活用した支援
- ⑤生命保険活用による資金準備
当センターは資金調達業務にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。また、生命保険コンサルタントと提携しており、最適の保険プランを提供させていただきます。
事業承継対策としての株式上場について教えてください。
株式上場とは、自社の株式を証券取引所に上場させ売買可能にすることを言います。一般的に株式上場により多額のキャピタルゲインを獲得することができるため、後継者が納税資金を確保できるという観点から事業承継対策の手法として活用することが考えられます。また、相続時精算課税制度を併せて活用することにより、株式上場により株価が上昇しても相続税額を低く抑えることが可能となります。