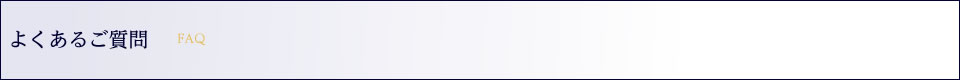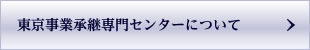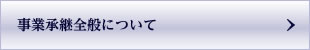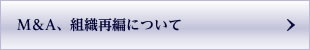株価対策について
株価引下げの方法としてどのようなものがありますか?
株価引下げの方法としては、以下のようなものが考えられます。
- ①オーナーへの退職慰労金の支給
- ②従業員持株会の活用
- ③投資育成会社の活用
- ④高収益事業の分離(組織再編)
- ⑤資産保全会社の活用
- ⑥保険の利用
いずれの方法による場合であっても過度な株価引下げは包括的租税回避と認定される可能性がある点、注意が必要です。また、株価引下に注力するあまり円滑な事業承継、事業運営に支障をきたすようなことになれば本末転倒となってしまいますので、必要、可能な範囲にとどめておくことが重要です。
自社株引下げの方法①オーナーへの退職慰労金の支給について詳しく教えてください。
オーナーに退職慰労金を支給することにより、利益が減少し、それに伴い、純資産も減少します。株式の評価方法である類似業種比準方式は会社の利益、純資産を用い、純資産価額方式は会社の純資産を用いて計算するため(詳細は「相続贈与について」Q6~をご参照ください)、オーナーに退職慰労金を支払うとその分株式の評価額が減少することになります。また、退職慰労金に係る所得税は、給与に比べて、低額であるこからオーナー側にも税務上のメリットがあります。
オーナーへ退職慰労金を支給する場合の留意点を教えてください。
役員退職慰労金は、取締役会に一任することを株主総会で決議し、「役員退職慰労金規程」に則り支払われるのが一般的です。従って、このような規程を設けていない場合は株主総会決議により定款を変更する必要があります。また、株価引下げの為に多額の役員退職慰労金を支払うと会社の決算数値が歪められることになるため、役員退職慰労金の額は社会通念上認められる範囲にとどめておくべきです。さらに、不相当に高額な役員退職慰労金については、損金不算入となります。相当かどうかは①従事した期間②退職の事情③事業の規模から見て相当かどうかを判断するものとされ、実務上は「在任期間×月額報酬×役員功績倍率」で計算されます。
株価引下げの方法②従業員持ち株会の活用について詳しく教えてください。
従業員持株会が自社の株式を取得する場合、株価は配当還元方式により評価されます(詳細は「相続贈与について」Q8をご参照ください)。配当還元方式は一般的に類似業種比準方式、純資産価額方式と比べ株価が低くなるため、それだけ株価引下げ効果があります。従業員持株会の株式取得には、①オーナーの株式を持株会に譲渡する方法②従業員持株会に第三者割当増資を実施する③自己株式を従業員持株会に譲渡する等の方法が考えられます。また、その他の効果として、安定株主の確保、従業員のモチベーションの向上が期待できます。
従業員持株会を活用する場合の留意点を教えてください。
従業員持株会を運営している中小企業は少数だと考えられます。従業員持株会の設立、運営には一定の手続とコストが発生します。また、オーナーが従業員持株会に株式を譲渡する場合、配当還元方式により相続税贈与税は低くなりますが、株式評価額自体が低下するため、手取金額が減少する可能性が高くなります。さらに、従業員持株会の持株割合についても留意する必要があります。10%未満に抑えるのが一般的だと考えられます。
設立後の留意点としては、節税のみを重視し従業員の福利厚生という本来の目的からはずれて形骸化すると税務上否認される可能性があるほか、持株会の独立性についても配慮する必要があります。
従業員持株会の設立について教えてください。
従業員持株会の設立手続きは以下のようになります。従業員持株会には大きく「民法の組合」と「任意団体による方法」とがありますが、現状、ほとんどが「民法の組合」であるため、「民法の組合」の従業員持株会の設立運営について説明します。
- ①計画立案
持株割合、拠出方法などを決定します。 - ②発起人の決定
- ③事務管理方法の決定
会員名簿の管理、入退会の処理等の事務管理を自社で行うか、外部に委託するかを決定します。 - ④規約等の作成
- ⑤発起人会、設立総会、理事会の開催
- ⑥取締役会の承認
- ⑦株主総会決議
第三者割当により持株会に株式を付与する場合等には株主総会決議が必要となります。
なお、民法上の組合となるため、登記、定款認証などの手続は不要です。
従業員持株会設立後の運営について教えてください。
従業員持株の運営手続は以下のようになります。
- ①従業員の入会
授業員は、通常入会申込書により加入します。 - ②会員名簿の作成
- ③給与天引きによる拠出金の徴集
- ④配当金の管理
通常配当金は再拠出に充てられます。 - ⑤入会退会管理
上記手続は、社内で運営される場合には、通常総務部が担当します。従業員持株会が形骸化すると税務上否認される可能性があるため、継続的に運営して行く必要があります。また、独立性が確保されていない場合にも、同様のリスクがあるため注意が必要です。
税務上の手続としては、持株会への配当金を支払うため会社では支払調書の作成が必要となります。持株会では、申告は不要ですが、「信託の計算書」を所轄税務署へ提出する必要があります。
自社株引下げの方法③投資育成会社の活用について教えてください。
投資育成会社とは、中小企業の資本の充実を図り、その成長発展を促進させることを目的として、中小企業投資育成株式会社法に基づき設立された株式会社を言います。投資育成会社を割当先として株式を発行した場合、その評価は、独自の計算により算定され、税法基準よりも低い価額となります。また、投資育成会社に割当てた分だけ発行済株式数も増加するため、全体として株価が低くなり、株価引下げ効果を期待できます。
投資育成会社を活用するメリット、留意点を教えてください。
Q8の株価引下効果の他にも、投資育成会社はインカムゲイン投資がメインとなりますので、安定株主を確保することができる、投資育成会社の融資を受けることにより社会的信用が向上する、各種セミナー、ビジネスマッチングを活用することができるといったメリットがあります。一方で、投資育成会社は中小企業の成長を促すことを目的としているため、融資を受けようする会社は成長性のある企業となります。従って、株価引下げのみを目的とした融資は難しいと考えられます。また、投資育成会社に対して継続的な配当を支払い続けなければならい点も留意が必要です。
自社株引下げの方法④高収益事業の分離(組織再編)について教えてください。
複数の事業を営んでいる場合に、高収益部門を分社化あるい完全子会社化し、完全親会社の株式を事業承継対象とします。株式の評価方法である類似業種比準方式は会社の利益、純資産を用い、純資産価額方式は会社の純資産を用いて計算するため(詳細は「相続贈与について」Q6~をご参照ください)、高収益部門を切り離すことにより、完全親会社株式の評価額引下げ効果が期待されます。また、完全親会社が保有する完全子会社株式の評価については含み益の42%が相続税評価額から控除されるため、完全親会社株式の純資産価額も減少し、完全親会社株式の評価額が引き下げられることになります。