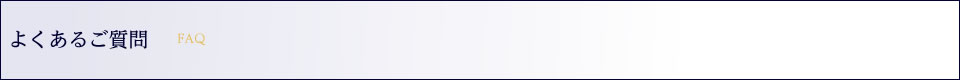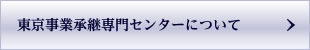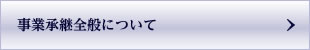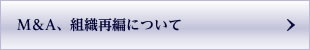相続贈与について
経営承継円滑化法について詳しく教えてください。
経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継の円滑化を図るために平成20年5月9日に制定され、その柱は、①遺留分に関する民法の特例②事業承継時の金融支援措置③相続税課税の特例措置の3つとなります。
経営承継円滑化法における、遺留分に関する民法の特例について詳しく教えてください。
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。事業後継者以外の相続人に遺留分を放棄してもらう場合、遺留権者(遺留分を放棄する相続人)が自ら家庭裁判所に申立て、許可を得る必要があり、手続が煩雑でした。そこで、経営承継円滑化法では、一定の要件を満たす場合、事業後継者が、推定相続人全員の同意を得て遺留分に関する除外合意、固定合意を、経済産業大臣に申請する遺留分の特例が認められています。ここで、除外合意とは、事業後継者が現経営者から生前贈与によって取得した自社株式を遺留分対象から除外する旨の合意を言い、固定合意とは、事業後継者が取得した自社株式について、遺留分算定の財産に算入すべき価額を固定することを合意することを言います。
除外合意、固定合意を経済産業大臣に申請するための要件を教えてください。
除外合意、固定合意を経済産業大臣に申請するための要件は、以下の通りです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 特例中小企業者 | 中小企業者のうち、3年以上継続して事業を行っていること。 |
| 旧代表者 | 会社の代表者であった者。 |
| 後継者 | 旧代表者の推定相続人のうち、当該旧代表者からの自社株の贈与を受けた者であって、会社の総株主の議決権の過半数を有し、かつ、会社の代表者であるもの。 |
経営承継円滑化法における、金融支援措置について詳しく教えてください。
経営承継円滑化法では、①中小企業信用保険法の特例②日本政策金融公庫等の特例が認められています。①中小企業信用保険法の特例の認定を受けた中小企業は、事業資金の信用保険枠を拡大でき、②日本政策金融公庫等の特例の認定を受けた中小企業代表者個人は、事業承継の際に必要となる資金を特別に低い利率で融資を受けることができます。
経営承継円滑化法における、相続税課税の特例措置について詳しく教えてください。
経営承継円滑化法では、一定の要件を満たす場合、①非上場株式にかかる贈与税の納税猶予の特例、②非上場株式にかかる相続税の納税猶予の特例を認めています。①非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例とは、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、贈与により「その会社の発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの非上場株式等」を取得した場合には、一定の要件を満たすことを条件に、特例受贈非上場株式等の贈与に係る贈与税の全額が、贈与者の死亡の日まで納税猶予されます。②非上場株式にかかる相続税の納税猶予の特例とは、経営承継相続人が取引相場のない議決権株式等を、経営者である被相続人から相続した場合には、一定の要件を満たすことを条件に、その会社の発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税額について経営承継相続人の死亡等の日まで納税が猶予されます。
経営承継円滑化法における、非上場株式にかかる贈与税の納税猶予の特例を適用するための要件を教えてください。
経営承継円滑化法における、非上場株式にかかる贈与税の納税猶予の特例を適用するための要件は以下のとおりです。
①経済産業大臣の認定
②経営者(贈与者)の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 代表者要件 | 会社の代表者であったこと。 |
| 支配株主グループ要件 | 贈与直前(贈与直前に代表権を有していない場合には代表権を有していた期間のいずれかのとき及び贈与直前)において、先代経営者(贈与者)及び先代経営者の同族関係者等の有する議決権数が、総議決権の50%超であること。 |
| 筆頭株主要件 | 贈与直前(贈与直前に代表権を有していない場合には代表権を有していた期間のいずれかのとき及び贈与直前)において、先代経営者(贈与者)が、後継者(受贈者)を除いた先代経営者の同族関係者等の中で最も多くの議決権数を有していたこと。 |
| 役員退任要件 | 贈与時までに、会社の役員を退任すること。(H27.1.1以降は、代表権を有していないことで足りる) |
③後継者(受贈者)の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 親族要件 | 贈与時において、先代経営者の親族であること。(H27.1.1以降廃止) |
| 成年要件 | 贈与日において、20歳以上であること。 |
| 代表者要件 | 贈与時において、その会社の代表者であること。 |
| 支配株主グループ要件 | 贈与時において、後継者および後継者の同族関係者等の有する議決権数が、総議決権数の50%越であること。 |
| 筆頭株主要件 | 後継者が、後継者の同族関係者等の中で最も多くの議決権数を有することとなること。 |
| 株式継続保有要件 | 贈与税の申告期限までに贈与により取得した株式のすべてを保有すること。 |
| 役員要件 | 贈与の直前3年以上継続して、会社の役員または業務執行役員であること。 |
④会社の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 従業員雇用要件 | 贈与時において、会社の常時使用従業員の数が1名以上であること |
| 事業要件 | 贈与時において、一定の資産保有型会社に該当しないこと、一定の資産運用型会社に該当しないこと。 |
| 非上場要件 | 非上場株式であること。 |
| 非風俗業要件 | 風俗営業会社に該当しないこと。 |
| 収入要件 | その会社の贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額が、0を超えていること。 |
| 拒否権付種類株式非保有要件 | 拒否権付種類株式が贈与時において、後継者以外のものが保有していないこと。 |
| 中小企業者要件 | 贈与時において、円滑化法2条に規定する中小企業者に該当すること。 |
⑤一括贈与要件
後継者へ一括贈与すること
⑥担保提供要件
贈与税の納税猶予税額と利子税の合計額に相当する担保を提供する必要がある。
⑦その他の要件
経営贈与承継期間(贈与税の申告期限から5年間)は事業継続要件と株式保有要件、経営贈与承継期間経過後は株式保有継続要件がある。
経営承継円滑化法における、非上場株式にかかる贈与税の納税猶予の特例を適用するための手続を教えてください。
経営承継円滑化法における、非上場株式にかかる贈与税の納税猶予の特例を適用するためのするには、経済産業大臣の認定が必要となります。また、経営贈与承継期間(贈与税の申告期限から5年間)は、毎年、経済産業大臣への報告が必要となります。所轄税務署長に対しては、贈与税の申告期限までに贈与税の申告が必要となります。また、担保提供が必要となり、さらに、経営贈与承継期間には毎年の継続届出書の提出、経営承継期間経過後は3年毎に継続届出書の提出が必要となります。
経営承継円滑化法における、非上場株式にかかる相続税の納税猶予の特例を適用するための要件を教えてください。
経営承継円滑化法における、非上場株式にかかる相続税の納税猶予の特例を適用するための要件は以下のとおりです。
①経済産業大臣の認定
②先代経営者要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 代表者要件 | 生前のいずれかの時点で、会社の代表権を有していたこと。 |
| 支配株主グループ要件 | 相続開始の直前(相続開始直前に代表権を有していない場合は、代表権を有していた期間内のいずれかのとき及び相続開始直前)において、先代経営者および先代経営者の同族関係者の有する株式の議決権数が、総株主の議決権数の50%超であること。 |
| 筆頭株主要件 | 相続開始の直前(相続開始直前に代表権を有していない場合は、代表権を有していた期間内のいずれかのとき及び相続開始直前)において、先代経営者が、後継者を除いた先代経営者の同族関係者等の中で最も多くの議決権を有していること。 |
③後継者要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 親族要件 | 相続開始直前において、先代経営者の親族であること。(H27.1.1以降撤廃) |
| 代表者要件 | 相続開始の日から5ヵ月を経過する日において、その会社の代表権を有していること。 |
| 支配株主グループ要件 | 相続開始時において、後継者及び後継者の同族関係者等の有する議決権数が、総議決権数の50%超であること。 |
| 筆頭株主要件 | 相続開始時において、後継者及び後継者の同族関係者等の中で最も多くの議決権数を有する事となること。 |
| 株式継続保有要件 | 相続開始から相続税申告書の提出期限まで引き続き、相続、遺贈により取得した株式のすべてを有していること。 |
| 役員要件 | 相続開始の直前において、会社の役員であったこと。 |
④会社の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 従業員雇用要件 | 相続開始時において、会社の常時使用従業員が1名以上いること。 |
| 事業要件 |
|
| 非上場要件 | 非上場会社であること。 |
| 非風俗営業要件 | 風俗営業会社に該当しないこと。 |
| 収入要件 | 相続開始の属する事業年度の直前の事業年度において、総収入額が0でないこと。 |
| 拒否権付種類株式非保有要件 | 拒否権付種類株式が、相続開始時において、後継者以外の者が有していないこと。 |
| 中小企業者要件 | 中小企業者に該当すること。 |
⑤担保提供要件
贈与税の納税猶予税額と利子税の合計額に相当する担保を提供する必要がある。
⑥その他の要件
経営贈与承継期間(贈与税の申告期限から5年間)は事業継続要件と株式保有要件、経営贈与承継期間経過後は株式保有継続要件がある。
経営承継円滑化法における、非上場株式にかかる贈与税、相続税の納税猶予の特例を適用するメリットを教えてください。
何よりも贈与税、相続税の納税を猶予できる点にあります。後に紹介する相続時精算課税とは異なり、この制度を適用した場合、相続税についても猶予されます。また、贈与税と相続税の納税猶予を併用することにより、以下のような場合、贈与税、相続税が免除されます。
- ①1代目経営者が2代目経営者に株式を一括贈与し、贈与税の納税猶予制度を利用する。
- ②その後、1代目の相続が発生した場合に、届出を提出して、贈与税を免除し、相続税について、納税猶予制度を利用する。
- ③その後、2代目経営者が3代目経営者に株式を一括贈与し、贈与税について納税猶予制度を活用する。この場合、2代目の相続税が免除される。
経営承継円滑化法における、非上場株式にかかる贈与税、相続税の納税猶予の特例を適用する際の注意点を教えてください。
Q19で説明した場合を除き、基本的には贈与税、相続税の納税猶予である点、注意が必要です。また、この制度を適用するためには、経済産業大臣の認定が必要であり、認定後も、経営贈与承継期間(贈与税の申告期限から5年間)は、毎年、経済産業大臣への報告が必要な他、税務署長へも届出書を継続して提出する必要があります。さらに、認定を受けるためには株式を担保提供する必要があり、認定後も要件を満たさなくなった場合には、利子税と併せ一括して納付しなければなりません。