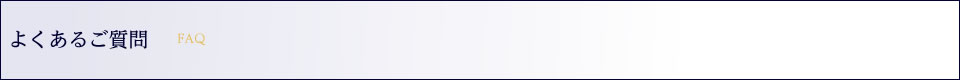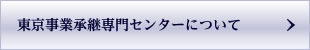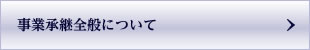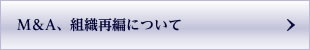相続贈与について
事業承継の各手法②贈与についてもっと詳しく教えてください。
現経営者が生前、事業後継者に株を贈与して事業を承継する方法です。贈与の場合には、事業後継者に贈与税が課されることになります。
贈与による事業承継のメリットを教えてください。
年間の贈与額が110万円以下の場合は非課税となります。また、現経営者が望む人物を後継者とすることができます。さらに、相続時精算課税制度を利用することにより、贈与税の課税を繰り延べることができます。
贈与による事業承継のデメリットを教えてください。
何よりも贈与税の税負担額が高額になるという点が挙げられます。具体的には贈与財産の価額に対し超過累進税率により、以下のように贈与税が課されます。
| 贈与資産の金額 | 控除額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10% |
| 300万円以下 | 15% |
| 400万円以下 | 20% |
| 600万円以下 | 30% |
| 1,000万円以下 | 40% |
| 1,500万円以下 | 45% |
| 3,000万円以下 | 50% |
| 3,000万円超 | 55% |
贈与における株式評価の方法を教えてください。
贈与における株式評価は、「財産評価基本通達」に基づいて行われます。具体的には、会社の規模等に応じて、大会社、中会社、小会社等に分類し、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式、これらを併用した方式により評価します。詳細は、Q7~をご参照ください。
贈与による事業承継の対応策を教えてください。
贈与による事業承継の場合、以下のような対応策が考えられます。
- ①株価対策 … 株価引下げ、従業員持株会の活用等
- ②納税資金対策 … 金融機関からの融資、生命保険の活用、経営承継円滑化法の基づく金融支援措置の活用、経営承継円滑化法の基づく納税猶予の特例等、相続時精算課税の適用
相続時精算課税とはどのようなものですか?
相続時精算課税とは、一定の要件を満たした場合、贈与財産から特別控除額2,500万円を控除した金額に、一律20%で贈与税を課税し、その後相続が発生した時に、当該贈与税と相続税を通算して納付する制度を言います。相続時精算課税を適用するための要件は以下のとおりです。
- ①贈与者は、65歳以上であること
- ②受贈者は、20歳以上の子または孫であること
相続時精算課税方式を適用するメリットをおしえてください。
何よりも贈与税の課税を相続時にまで繰り延べることができるという点にあります。また、2,500万円の特別控除が認められている他、税率も一律20%となっており、暦年贈与と比較すると税負担額が低く設定されています。また、相続時精算課税方式は各個人毎に適用できるため、例えば夫婦で相続時精算課税方式を選択し子に贈与する場合、合計5,000万円まで贈与税が課されないことになります。さらに、相続発生時、相続時精算課税方式の対象となった資産は相続時精算課税適用時の時価で評価されるため、相続までに時価の上昇が確実な資産を相続時精算課税方式により贈与していれば、その分、税負担額を小さくすることができます。
相続時精算課税方式を適用する場合の注意点を教えてください。
相続時精算課税はあくまでも贈与税を相続時まで繰り延べる制度に過ぎず、免税制度、減税制度ではない点注意が必要です。また、相続時精算課税方式を一旦選択すると暦年贈与との併用は認められないため、その後暦年贈与の基礎控除110万円は控除できません。さらに、相続発生時、相続時精算課税方式の対象となった資産は相続精算課税適用時の時価で評価されるため、相続発生時までに時価が下落していた場合、税負担額が大きくなります。
遺言について教えてください。
相続が発生し遺言が残されている場合には、基本的に遺言の内容が優先されます。従って、相続による事業承継を選択した場合、遺言により、現経営者の意思をある程度反映させることができます。遺言には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。
①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の違いを教えてください。
①自筆証書遺言は、被相続人が遺言内容、日付等すべてを作成し自著押印して作成します。②公正証書遺言は、公証役場で、公証人に遺言内容を口述し、公証人が作成します。③秘密証書遺言は、被相続人が遺言書を作成し、内容を伏せたまま公証役場で公証人に遺言書であることを証明してもらいます。各遺言書のメリット、デメリットをまとめると以下の通りです。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 記載者 | 遺言者 | 公証人 | 代筆も可 |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 費用 | ほとんどかからない | 公証役場手数料 | 公証役場手数料 |
| 保管 | 遺言者本人 | 原本:公証役場 正本:遺言者本人 |
遺言者本人 |
| 紛失、変造 | 最も高い | ない | 変造はないが、紛失はありえる |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 内容の秘密 | 保てる | 保てない | 保てる |
| 無効の危険性 | 法定書式に不備がある場合無効になる可能性がある | ない | 法定書式に不備がある場合無効になる可能性がある |
遺言を作成する際の留意点を教えてください。
遺言を作成する際には、①法的形式に不備があった場合には無効となる可能性がある。②遺留分を侵害した場合には、他の相続人に遺留分減殺請求権が認められるため、遺留分に配慮するといった点に留意する必要があります。これらを考慮すると公正証書遺言による遺言が最も安全性確実性が高いと思われます。当センターでは専門の司法書士が公正証書遺言の作成に対応致しますので、お気軽にご相談ください。